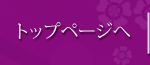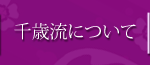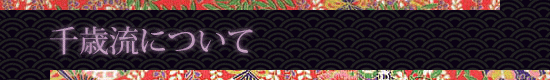
序章 二代目 宗家 千歳旭梅
千歳の詩は初代宗家が二巻を発行しており、この度は三巻目にあたります。
ふりかえりますと過去の思い出は現在へと広がり、その長さは限りがありませんのでこのはしがきにて過去の打ち切りとし、三巻目は二代目旭梅の責任において七十五周年の記念誌としたいと思います。
初代旭梅は少女時代、生みの親と育ての親の間を親同士の都合で、行ったり来たりの辛い環境にありました。
義父は旭梅が生まれる前に日露戦争に出征し、今度生まれる子(義母の子)を自分の子にする様に言い残し出征、無言の凱旋となりました。
実父は利発な「むめ」(旭梅)を溺愛し孫も、どの孫よりも可愛がってくれたと言います。
私も祖父の背中で聞いた子守唄が記憶に時々蘇ることがあります。
寂しい生い立ちの母は、五人兄弟の一人娘として生まれた私をどんなに大切に育ててくれたかを感じつつも、それを当たり前のように思いながら私は成長しました。
父は山梨県塩山の或る素封家の三男に生まれ、当時にしては珍しく早稲田大学の法科を卒業し警視庁に勤務しておりました。
ここでもう触れることもないであろう父を思い出したいと思います。
小学校の遠足には必ずついてきて友達との写真を写して呉れて私にはそれが誇らしく、また嫁に行った娘を、私がいくつになっても「一人娘です」と紹介するのが恥ずかしくて、「お父さんそれだけはよして」と言ったものでした。
明治生まれの父はコーヒーが好きで私とコーヒーを飲むときの、優しい笑顔は忘れることはできません。
母が先に逝ってしまい、何故もっと傍にいてあげなかったのかと悔やまれてなりません。
母は坊ちゃん育ちの父がはがゆく、母の目を通して父を理解していた私は母と兄弟に厳しい父に唯一反抗できる存在でもあり、父の愛をあまり身に沁みることができなかったのかもしれません。
しかし戦時中、英語廃止のさなか私の母校(小松川高校)が進学校にも拘わらず英語組と普通組に分けられ、退役将校でありながら父は「英語組のクラスに行かなければ学校に行かせない」と私を叱りました。
その反面お花、茶の湯音楽にも理解があり、習わせるだけでなく、時々は相手も務めてくれました。
卒業後もこれからの女はお嬢さん育ちだけではいけない、と美容学校の草分けであるマリールイズ美容学校(フランス大使館付きの美容師として来日)に入学させてくれました。
これには母が猛反対でしたが資格だけとり開業しない、という約束でしぶしぶ許してくれました。
振り返ってみますと、終戦後焼け出され長男も戦死の中で、ピアノも音大の先生につかせて呉れた父はどんなに私を愛していたのでしょう。
育ちの違いのせいかあまり反りが合わなかった父母も私の話の時だけ話が合った、と母は笑い、父が「恵子は私似だ」で一件落着だったとか。
千歳流のお蔭で母には親孝行の真似事は出来ましたが、父には何もしてあげられなかったのが悔やまれます。
ただ一枚父に着せたかった大島を、お正月に、と箪笥にあったのを涙ながらに亡骸にかけたのが唯一の親孝行でした。
膝を崩したことのない父は母の死後も私に甘えることもない父に「お父さん私に甘えないで誰に甘えるの?」と泣いたこと。
お父さん覚えていますか?
数日後「今度は何時来るの?」「来週来ます。お兄さん達が付添いさんを頼むと言っていたけど、お父さんが早く言って呉れれば、予定に入れたのに。」
この会話が最後で数分後に兄の必死の手当の甲斐なく天国に召されてしまいました。
実家で生まれた私の娘(旭洋)を膝に乗せて大事大事にお風呂に入れてくれたお父さん有難う。
今もその姿が目に浮かびます。もう一度お父さん有難う。